eBayにおける関税の支払いフローまとめ
eBayを通じて海外取引を行う場合、バイヤー(購入者)が負担する関税や輸入税の支払い方法は、国や地域、
さらには商品の価格・カテゴリによって大きく異なります。なかには、購入時にあらかじめ徴収されるケースもあれば、
到着時に配送業者や税関が追加請求するケースもあり、複雑になりがちです。
そこで本記事では、主要な国や地域の一般的な支払いフロー、eBayが提供するグローバル・シッピング・プログラム(GSP)などを含め、
関税の仕組みや注意点を約5,000文字程度でわかりやすくまとめました。ぜひ参考にしてください。
目次
1. はじめに
eBayでは、世界中のバイヤーと直接取引できる魅力がある一方で、
関税や輸入税、さらには通関手続きに関連する費用(通関手数料、税関代理費用など)が絡んでくるため、
国内取引ではあまり考慮しないような要素にも注意が必要です。特に、バイヤーと出品者の間で
「関税は誰が支払うのか?」、「いつ・どうやって徴収されるのか?」といった問題が起こりやすく、
事前の知識が不足しているとトラブルに繋がりがちです。
ほとんどの場合、国際取引における関税や輸入税は
「バイヤー(購入者)が負担する」
というのが大原則になります。しかしバイヤー側がその認識を持たずに購入したり、
国によっては事前徴収と到着時徴収が混在していたりと、フローが複雑になりがちな点に注意しましょう。
以下では、主要な国・地域ごとに「支払いの流れ」や「免税枠」の目安を紹介していきます。
2. アメリカ合衆国:de minimis規定と通関時の支払い
アメリカは「de minimis(デ・ミニミス)」という規定を採用しており、
\$800以下の商品については関税が免除されるケースが一般的です。
これは個人輸入に対して非常に優遇された制度であり、
高額商品でなければバイヤーは関税を支払わずに済む可能性が高いと言えます。
ただし、アルコールやタバコ製品、その他特定の規制品目については
\$800以下でも課税対象になることがあるため、すべてが無税になるわけではない点には留意しましょう。
また、\$800を超える金額の商品を輸入した場合や、
コマーシャルユース(商用)と見なされる場合には関税がかかり、
配送業者(DHL、FedEx、UPSなど)が通関代行料を上乗せして
バイヤーへ請求するのが一般的な流れです。
具体的には、商品到着のタイミングや事前通知を経て
バイヤーが関税を支払うことで荷物が受け取れるようになります。
配達時に配達員に現金やクレジットカードで支払うパターンや、
事前にオンライン決済で関税を納めるパターンがあり、
これは配送業者や税関の運用状況に左右されます。
3. ヨーロッパ(EU):IOSSと150ユーロの関税ライン
EU(ヨーロッパ連合)では、2021年7月に大きな制度変更があり、
かつては22ユーロ以下の輸入品に対するVAT免税が存在していましたが、
現在では廃止され、すべての輸入品にVATが課されるようになりました。
一方、関税は150ユーロを境目に課されるかどうかが変わるため、
商品の価格帯によってバイヤーの支払いフローが大きく異なります。
具体的には、150ユーロ以下であれば関税は免除されるケースが多いものの、
VAT(付加価値税)が発生します。VAT率は国ごとに異なり、
例えばドイツは19%、フランスは20%、イタリアは22%といった具合に様々です。
さらに、海外出品者(セラー)やプラットフォームが
IOSS(Import One-Stop Shop)に登録している場合、
バイヤーは購入時点でVATを支払う形になります。この仕組みにより、
商品到着時に追加請求が発生しないメリットがある反面、
出品者がIOSSに正しく対応していないと、バイヤーが到着時に想定外の費用を請求されるリスクもあります。
150ユーロを超える商品の場合は、関税とVATが両方かかるため、
通関時にバイヤーがまとめて支払うパターンが多く、金額の大きい取引では注意が必要です。
4. イギリス(UK):135ポンド基準とVAT徴収
イギリスはEUを離脱(Brexit)したことにより、
従来のEUルールとは異なる独自の制度を運用しています。
大きなポイントは、135ポンド以下の輸入商品について
海外出品者やプラットフォームがVATを代行徴収する仕組みが導入されている点です。
つまり、バイヤーは商品購入時に「商品代金 + 配送料 + VAT」を合わせて払うことで、
到着時の追加負担をなくすことができます。
一方、135ポンドを超える商品の場合、
従来の国際取引と同様にバイヤーが通関手数料や関税、VATを
到着時に別途支払わなければならないフローになることが多いです。
イギリスの標準VAT率は20%ですが、
食品や子供服など一部品目は軽減税率が適用される場合があります。
加えて、EUとの間で通関手続きが変わったこともあり、イギリス向けの配送では
申告書類の作成や書き方を間違えると配送遅延や返送が発生するケースが報告されています。
関税支払いとは直接関係なくとも、
正しいHSコードの記入やインボイスの内容が非常に重要です。
5. カナダ:州税と連邦税、HSTの複合課税
カナダでは、\$20以下の輸入品については免税になることが多い反面、
それ以上の金額になるとGST(連邦消費税)や
PST(州税)、あるいは両者を統合した
HST(統合売上税)が課されます。州によって適用される税率や仕組みが異なるため、
バイヤー自身が正確な税額を事前に計算するのが難しいケースも少なくありません。
高額品や特定のカテゴリ(衣類やアクセサリー、電化製品など)には別途関税が上乗せされ、
税関手数料と合わせて請求されることがあります。一般的には、
配送会社が通関を代行し、バイヤーが荷物を受け取る際に立て替え費用を含めて支払うパターンです。
配送業者によってはオンラインで事前に支払う仕組みを提供しているところもありますが、
地域やタイミングにより対応が異なります。
カナダのバイヤーからは、到着時に税金が高くて驚いたという声もあるため、
出品者としては商品説明欄やメッセージで「追加費用がかかる可能性がある」旨を
しっかり案内しておくことがトラブル回避に繋がります。
6. オーストラリア・ニュージーランド:GSTの取り扱い
オーストラリアでは、A\$1000未満の輸入品について基本的に関税がかからない一方、
GST(消費税)10%がかかることがあります。特に、海外EC事業者が一定額以上の売上を持つ場合、
「海外事業者がGSTを代行徴収してオーストラリア税務当局に納付する」ことが
義務付けられるケースがあります。eBayなどのプラットフォームで購入する場合、
バイヤーが商品代金に上乗せされた形でGSTを支払うことで、到着時の追加コストが少なくなる仕組みです。
ニュージーランドでも基本的にNZ\$1000以下の輸入が多いですが、
やはりGSTの取り扱いが整備されており、ある程度の金額を超えると
関税も含めた通関手続きが必要になります。国ごとに細かい規定が異なるため、
出品者としてはバイヤーに「通関時に追加費用がかかる可能性」を知らせることが望ましいでしょう。
7. 南米・アジア:高関税や複雑な通関手続き
南米(ブラジル、アルゼンチンなど)やアジアの一部地域(インドネシア、フィリピン、中国など)では、
非常に高い関税率や煩雑な通関プロセスが敷かれていることが多いです。
例えば、ブラジルでは輸入品に対してICMSという州税などが上乗せされ、
場合によっては商品の価格以上の税金が発生することすらあります。
また、通関時に別途書類(インボイスやライセンス、認証関係など)を要求されるケースや、
誤った申告によって長期間税関で保留されるケースも珍しくありません。バイヤーが理解を深めていないと、
到着時に思わぬ高額請求を受けて受取拒否につながるリスクが高まります。
返送されても発送元に辿り着くまで時間がかかるうえに、返送料や保管料が加算される場合もあるため、
出品者としては十分注意しておく必要があります。
アジア圏でも、韓国は「個人通関番号」、
中国は「税関登録ID」など、
国・地域ごとに独自のルールがあり、少しでも不備があると通関がストップすることがあります。
これらは関税支払いフローにも影響するため、
バイヤーとの事前コミュニケーションが不可欠と言えるでしょう。
8. eBayのGSP(グローバル・シッピング・プログラム)とは
eBayには、Global Shipping Program(GSP)と呼ばれるサービスがあります。
これは、米国のeBay物流拠点を通じて海外発送する仕組みであり、
関税や輸入税を事前に見積もり、バイヤーが購入時点でそれらの費用を含めた
「合計金額」を支払う形式を採用するのが特徴です。
出品者にとっては「国内発送」扱いで米国のGSP拠点(Kentucky州など)に送るだけで、
そこから先の国際配送や通関手続きはGSPが受け持ちます。バイヤーとしても、
到着時に追加費用が発生しない(もしくは最小限で済む)ため、安心感を得られるメリットがあります。
ただし、送料・手数料が高く見積もられる傾向があり、
バイヤーが敬遠する場合もあるため、一長一短と言えるでしょう。
日本在住のセラーが利用する場合は条件がやや限定されるものの、
今後eBayが新たな国際配送サービス(eBay International Shipping)を積極展開していることもあり、
あらかじめ関税を代行徴収するオプションが増えていくと予想されます。
その際のメリットとしては、配送トラブルや追加請求によるクレームを大幅に減らせる点が挙げられます。
9. まとめ
eBay取引において、関税や輸入税の支払いフローは国や地域、商品価格帯によって大きく変わります。
一般的には、次のようなパターンが見られます:
- アメリカ:\$800以下は関税免除(de minimis規定)。超過すると通関時にバイヤーが支払い。
- EU:150ユーロ以下は関税免除だがVATがかかる。IOSS登録がある場合、購入時にVAT徴収。
- イギリス:135ポンド以下ならプラットフォームがVAT代行徴収。それ以上はバイヤーが通関時に支払い。
- カナダ:\$20を超えるとGST・PST・HSTが適用されやすく、到着時にバイヤーが支払い。
- オーストラリア/ニュージーランド:一定金額以下は関税がかからないがGSTが発生する場合がある。
- 南米・アジア:関税率が高い国が多く、通関手続きも複雑。到着時支払いが主流だがリスクも大きい。
- eBay GSP:購入時に関税・輸入税推定額を上乗せして徴収し、到着時の追加負担を減らす方式。
出品者としては、「関税・輸入税はバイヤー負担」という原則を明確に示しつつ、
できるだけ正確なインボイス(納品書)やラベルを用意し、申告漏れや過少申告を避ける必要があります。
バイヤーとのコミュニケーションで
「国によっては思いのほか高い税金が課される場合がある」といった注意喚起をしておくと、
後々のクレームリスクを減らせるでしょう。
また、国際物流や関税制度は政治・経済状況などにより変化しやすいため、
eBay公式ヘルプや物流企業(DHL、FedEx、UPSなど)の最新情報を随時チェックし、
スムーズな取引ができるよう配慮しておくことが重要です。最終的にバイヤーが税金を支払うからといって、
出品者がまったく気にせずにいると悪い評価や返送トラブルに繋がりやすいため、
グローバル市場で長期的に取引を続けるなら、最低限の知識を身につけておくことをおすすめします。
※本記事は執筆時点の一般的な情報をもとにしています。実際の取引にあたっては、必ず各国の税関ウェブサイトやeBay公式ガイド、最新の法令を確認し、正確な情報を入手してください。

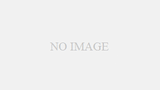

コメント